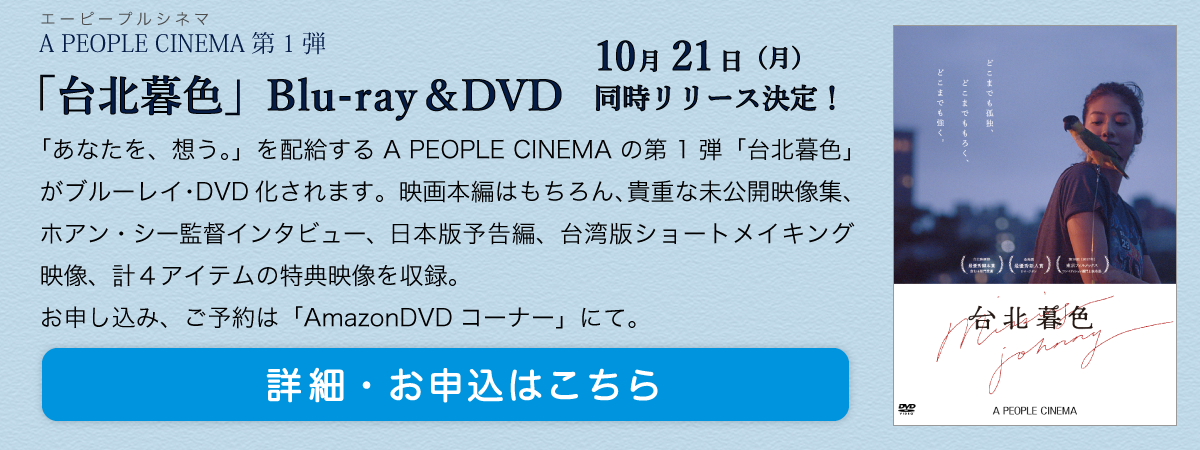STORY
親しい先輩の訃報の知らせから、久しぶりに大邱(テグ)を訪れた北京大学教授のチェ・ヒョン(パク・ヘイル)。亡くなった先輩との7年前の旅を思い出したヒョンは、衝動的に、そこからほど近い慶州(キョンジュ)へと向かう。以前と変わらず、美しい緑に包まれた古墳が並ぶ街を懐かしむヒョン。彼にはどうしても確認したいものがあった。それは、茶屋にあった一枚の春画。その茶屋を訪れたヒョンは、美しい主人・ユニに出逢う。そこに春画は、もうなかった。ユニによれば、7年前からそれは存在しないという。ヒョンはその後、かつて一夜を共にしたことのある後輩の女性をソウルから呼び出すものの、衝撃的な秘密を打ち明けられる。そして、ユニにも哀しい過去があった……春画を探すヒョンがやがて辿り着く意外な結末とはーー。エンディング曲の題名は「サラン(愛)」。詩情緒に満たされるラスト……。
INTERVIEW
チャン・リュル
慶州では、生と死が穏やかに共存している。

この作品は1995年に私が初めて韓国を訪れたときに、知人の案内で慶州に連れて行ってもらったことがきっかけで生まれました。慶州で入った伝統茶屋の壁に春画がかかっていて、私よりもかなり年上だった知人たちが絵についてお店の方に冗談を言ったんですが、その主人はまったく顔色を変えずに丁寧にお茶を淹れていました。それがとても印象的でした。そして、7年後に再び慶州を訪ねたところ、茶屋はありましたが春画はなくなっていました。
慶州という街は王陵や墓地が1ヵ所にあるのではなく、都市全体にあるんです。今でこそそれらは文化財として大事にされていますが、1995年当時はそこでみんなが酒を飲んだり遊んだりしていたので、それを見て、生と死が穏やかに共存しているんだなと思いました。街の空間に魅力を感じ、そこに入り込み、そのときの記憶がずっと残っているという感じがありました。
映画というのは事実を撮るものではなく、記憶を映すものだと思うんです。そういう意味では記憶に関する映画だとも言えるでしょう。この世とあの世があるとしたら、その二つの世界自体も記憶の中にあるのかもしれません。記憶には事実もありますが、別の考えや新しい時間が入ってくるので、必ずしも事実とは言えないと思います。日常生活の中で確かに写真を撮ったと記憶していたはずなのに、後で見てみるとその写真がない、というような経験は誰にでもあると思います。
見た方からはヒョンとユニはこの世に存在していないのではとも言われました。私自身は撮影中や編集段階では存在していると思っていましたが、撮り終えた後はこの世とあの世の区別がつかなくなっていた気がします。彼らはこの世にいるかもしれないし、いないのかもしれません。ヒョン役のパク・ヘイルさんもユニ役のシン・ミナさんも、自分の中から新たな可能性を引き出そうとして本当に熱心に臨んでいました。作品に完全に没頭し、役になり切ってくれてありがたかったです。
パク・ヘイル
正直で、真実味のある姿が引き出された。

チャン・リュル監督とはユン・ジンソさんから紹介されて会いました。監督のもっている情緒が自然に伝わってきて、この監督とぜひ仕事をしたいという気持ちになったんです。この映画は監督が過去に慶州に来て経験した出来事、その記憶を作品にしようとしたと聞いて、それなら私という俳優が監督の過去の記憶を代わりになぞってみたらどうかと考えました。
クランクイン前、監督と一緒に慶州へ行って何日か過ごしたことがとても助けになりました。それまでは修学旅行で訪れる場所という以外、慶州について特に思いはなかったんですが、ゆっくり散策しながら街を味わういい機会になったようです。墓が街中にあり、そこに普通に生活している人々の家があって、両者が共存している日常の姿が心に残りました。
撮影中は監督に似るようにとずっとそばにいました(笑)。私が演じたヒョンは教授ですがどこか突飛な面がある人間で、そういうさまざまな面がある人物だというのがとても面白かったです。そうしたキャラクターを私が楽しく感じて演じていたので面白い場面もできましたし、私がそう感じているのを監督がうまくキャッチしてくださったんだと思います。監督と仕事をしてみて、自分の繊細な部分に気づいて、より正直に自分という人間の感情を表現できるようになったと思います。監督の独特な演出の方法により、正直で真実味のある姿が引き出されたような気がして、それが興味深いことだなと感じています。
シン・ミナ
どこか訳ありな感じの女性を演じるのは新鮮でした。

最初にオファーを受けたとき、難しいなと思いました。というのは、チャン・リュル監督はきちんとした台本なしに、ディティールやセリフも現場で修正しながら作っていくと聞いていたからです。ただ、監督の前の作品を見てみて、どんな風に撮るのか好奇心が湧いてきました。普通とは違うスタイルで撮っているということで、私も心を開いて臨もうと考えました。
撮影中はセリフも動線もその場で監督と話をしながら決めていくことが多かったです。モニターを見ながらシーンごとに一緒に作っていく中でだんだん監督の意図が分かってくる、そういう経験は初めてでとても面白かったですね。私が演じたユニについては映画で描かれた通りで、監督からは背景の詳しい説明は特にありませんでした。それで自分なりに、愛する夫を亡くして、その悲しみが癒えたとまでは言えませんが、お茶に接することで気持ちが少し穏やかになっていると考えて、その点に気を遣って演じました。
監督には「自分では遅すぎるんじゃないかと思うくらい、もっとゆっくり物を掴んでほしい」とよく言われました。それが面白かったですね。なんだかスローモーションみたいにゆっくりだと感じたんですが、大きな画面で見たらそれがユニの特徴を表しているんだなと思いました。それまでの私は成熟した姿をお見せすることがあまりできませんでした。ですから、夫を亡くした過去があり、どこか訳ありな感じの女性を演じるのは新鮮で楽しかったです。